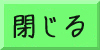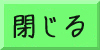まるびのナイフ考 その2 ブレード材について
知っての通り、ナイフとは物を切るための道具です。
一般に、物を切る部分がブレードでそれを保持するハンドルとで形成されます。
切るための性能を左右するのがブレードの材質なのですが、私の独断と偏見で材質について少し説明し
ましょう。
まずブレードの材質の主成分は鉄です。 原子番号26の元素ですね。
この鉄に炭素(カーボン)が混ざっているのが鋼(スチール)です。
ようするに鋼とは鉄と炭素の合金のことです。
鉄は炭素の含有量が増すにつれどんどん硬くなりますが、脆くなるという性質があります。
この硬さと脆さのバランスを上手に取ってブレードの材料にします。
鋼(はがね):
で、ナイフのカタログ等を見ると目に付くのが、「ブレード材カーボン」等といった記述ですが、
カーボン(炭素)だけでブレードを作ることは非常に困難です。
もう少しマシな記述だと「ブレード材カーボン鋼」或いは「炭素鋼(カーボン・スチール)」とい
うもの。
実はこれも変で、先にも書いた通り鋼とは鉄と炭素の合金ですから、炭素鋼、或いはカーボン・スチール
とは「砂糖入りの砂糖水」と言っているのと同じです。 変ですよね。
硬度を上げるため炭素含有量の高い鋼、つまり高炭素鋼(ハイ・カーボン・スチール)のことを省略して
いるのでしょうけど。
まあ細かい事はさておき、鉄というのは高純度にするのは非常に難しくて精錬の過程でいやでも炭素や
その他の不純物が混入してしまうのですが、この不純物や炭素の含有量を適切にコントロールした材料
に熱処理を加えて目的の性能を得たものをブレード材として使用します。
更にはコバルトやバナジウム等をも加え性能を上げた各種の鋼材があります。
しかしながら高炭素鋼は刃物としては充分な性質を持っていますが、実使用上に於いて大きな欠点があ
ります。
酸化しやすい、つまり錆びる(腐食する)ということ。
ナイフは使用する状況により水分や塩分等に接することがあるために腐食してしまうのです。
特にそういう条件でなくとも空気中の水分と酸素により放置しているだけでも腐食します。
これを防ぐためせっせと錆び止め油を塗るなどの手入れが必要になり面倒ですよね。
因みにガーバーのAシリーズやCシリーズ等は良質なクローム・メッキを施しており非常に優秀な耐食性
を実現しています。 私の数十年の使用経験で全く錆びていません。 これは見事です。
「なんでやねん、刃先は研ぐからメッキは無いやろ?」と思う方も居られるでしょうけど、ある専門家の
人に聞いた話では「良好に熱処理されたM2鋼はそれなりに耐食性がある」とのことでした。
残念ながら最近はこのような処理をしているメーカーはありません。
ブレードに塗装しているメーカーもありますが、ナイフは擦れますので安っぽい塗装だと長持ちしません。
まぁ良い塗装(表面処理)によってはある程度の効果はあるでしょうけど。
大抵は塗装は錆び止めではなくブレードの仕上げの悪さを誤魔化すためのものです。
ステンレス:
腐食は刃物にとって致命的で、ぱっと見には錆びていないように見えても刃先の見えない部分が錆びて
切れ味を落とす場合もあります。
この腐食を防ぐ(耐食性を上げる)ため、鉄にクロムやニッケルといった各種金属を混入します。
これがステンレスです。
厳密には、一定量以上のクロムやニッケルを含むものをステンレスと呼びそれ以下は耐食鋼と呼びます。
クロムの含有量が上がるほど耐食性も上がるのですが、残念なことにクロムが多すぎると硬度が上がらな
くなりますので、これまたバランスが難しい。
このあたりが材料メーカーの工夫のしどころで、各社色々な製品を開発しています。
この金属成分によって後述の熱処理が異なります。
しかし同じ成分が含まれていたとしても他の不純物の量によっても特性が変わります。
ちゃんとしたメーカーのものは、成分はもちろんのこと不純物等の量も規定管理されています。
中国製の安価な同等品が本来の性能が出ないのは不純物の除去が不充分なためだと聞いたことがあります。
最近では粉末冶金製法での高性能な刃物用ステンレスが開発されており、これらはスーパー・ステンレス
と呼ばれたりします。
熱処理について:
熱処理とは一般に焼き入れと呼ばれる処理で、金属を高温にしてから急冷することにより硬度を上げること。
これをしないといくら高価な材料でも本来の性能(硬さ)を得られません。
ある人が「熱処理されていなければ、ナイフの形をしたただの鉄板」と言っていましたがその通りです。
適当に熱してから油や水に投入することである程度硬くはなりますが、金属によって温度管理はメーカー
が指定しており、厳密な環境で温度管理することで目的の性能を得られます。
因みに私が自作に使う材料はATS−34ですが、真空焼き入れという手法で行います。
業者の方に聞いた話だと、真空炉の中のどの位置かによっても微妙に出来あがりが異なるそうです。
この熱処理については一つ厄介なことがあります。それは見た目で良否がわからないこと。
いくら高価な材料を使用したナイフであっても熱処理が適切でなければ本来の性能は出ないのですが、
見た目でそれがわからない。
そこそこの硬さになってはいるので尚更わからない。
こればっかりはメーカーを信じるしかないので、見えない所を手抜きする国民性がある国の製品を
私が避けるのはこのためです。
更に言うと鋼材も何を使っているか信用できませんし。
硬さについて:
前述の熱処理が終わると材料は硬くなります。
その硬さを調べる方法には、モース、ビッカース、ロックウェル等があります。
一般にナイフ鋼材の硬さの指標は「ロックウェル硬度計のCスケール」が使われ、これがHRCという
単位です。
HRC55や、HRC60などといったもので、数値が大きいほど硬いわけです。
この数値を重要視するHRCオタクは「55だと使い物にならない」とか「60あるからいい」とか言う
訳です。
しかし実際にカタログ・スペックの硬度が出ているかを確かめるのは困難で、これもメーカーを信じる
しかなく自己満足の世界です。
私が依頼した熱処理業者は一本ずつ硬度測定してくれており測定値を記したタグがついています。
しかし、業者曰く「表面は硬さが出る傾向があり、厳密には表皮を少し削って測定しないといけない」
と言っていました。
それほど微妙なもんなんですね。
切れ味について:
ネット等でよく「炭素鋼はよく切れる、ステンレスは切れない。」というアホな記述を目にします。
何を根拠にあのようなデタラメを吹聴するのでしょうか。
優秀なステンレスが存在しなかった大昔ならばいざ知らず、現代に於いてカッターナイフやカミソリ、
医療用のメスもステンレスです。 素晴らしく切れますよ。
確かに電子顕微鏡で組織を調べればステンレスはクロムの原子が大きいので刃先の細かさの違いはあるで
しょうが、あの人たちはこの差を体感できるのでしょうか?
あの人達は目隠ししてステンレスと炭素鋼の差を判別できるのでしょうか?
私に言わせれば、大ウソつきかシッタカですね。
それなりにマトモ(熱処理を施された)なステンレスと炭素鋼で切れ味に体験できる差は無いと断言でき
ます。 それどころか、ZDP189、ATS34、カウリX等々、炭素鋼よりも優秀なものが多数存在
します。
ネットには誤った情報も多いので安易に信じ込まないよう注意してください。
研ぎについて:
残念ながら現在ではどんな優秀な鋼材でも多かれ少なかれ必ず磨耗します。
なので、やがては研がねばなりません。
相変わらずネット等で「炭素鋼は研ぎやすく、ステンレスは研ぎにくい。」という変な記述があります。
旧式の水砥石しか無かった大昔の人の話は無視して21世紀の話をしましょう。
以前、私はアーカンサスという油砥石を使っていましたが、今では使っていません。
なぜならば現代では非常に優秀な砥石があるからです。
セラミックやダイヤモンド砥石がネットやホームセンターで簡単に手に入る世の中になったからです。
これらの砥石であれば、ステンレスなども難なく研ぐ事ができます。
(高価なスーパー・ステンレスならちょっと時間はかかりますが。)
つまり、何が言いたいかと言うと、「研ぎに関して高炭素鋼かステンレスかを気にする必要は無い」です。
但し、前述のような優秀な砥石があれば、の話ですが。
箱出し?:
最後に「箱出しで良く切れるから云々」ということについて書きます。
これまたネットで「箱出しからよく切れるので・・・・・」と。
箱出しでよく切れるかどうかと、良いナイフかどうかと何の関係が?
どんな鋼材でも安物のナイフでも研げばそれなりに切れます。
つまりメーカーがちゃんと研いでくれているだけのことであり、ナイフが良いかどうかとは全く別の問題
です。 (まあ、親切っちゃあ親切ではありますが。)
良いナイフ(鋼材)とは切れ味が持続するかということ。
そしてナイフは必ず研ぐものであり、ナイフを買ったらまず自分の好みの刃付けをするのが漢。
なのでカスタムナイフ等は、ユーザーが自分の刃を付けるのを前提にしているので刃付けはあまりしてい
ないのです。 (例外もありますが。)
無駄に研ぐことはしませんよ、なぜならば“研ぐ”=“減る”ということですから。
従って、箱出しで云々は意味の無いことだと思ってくださいね。(まあ、親切ではありますが。)
但し、「いや、オレは研いだりしない、買ってそのまま使う。切れなくなったら買い替える。」
という人ならば話は別ですが。