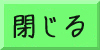万年筆用インクについての基礎知識
万年筆にとって欠かせないのがインクです。当然です。
色んなメーカーから沢山の種類のインクが発売されており、
どのインクを使うかというのも万年筆の楽しみの一つでもあります。
ところが各万年筆メーカーは純正以外のインクを使用した場合は保証しないことになっています。
つまり「ウチの万年筆を使うんやったら、ウチのインクだけしか使わなあかんで。」
「他のインクを使って変なことになっても知らんよ。」です。
これは正体の分からない変なインクの使用で万年筆に不具合が起こることを避けているわけですね。
まあ、メーカーとしてはこのように言うのは当然でしょう。
しかしながら必ずしも気に入った万年筆の純正インクに気に入った色があるとは限りません。
「ペンはA社がええけど、インクはB社のがええがな。」ってことはよくあることです。
なので、「好きなインクを使う、その結果、万年筆が溶けようが爆発しようが一切文句は言わんよ。」
という勇気ある人たちは保障など無視して自由なインクで楽しんでいます。
私もその一人です。
但し、こういう場合にはメーカー保障が受けられなくなりますので注意してくださいね。
過去に万年筆を破壊する凶暴なインクがあったのも確かです。
でもこれはかなり特殊な例であって、最近の一般的なメーカーのインクで問題が起きたのは聞いたことがありません。
しかしながら、好きなインクを自由に使いたい人は一応自己責任ということでこの先を読んで下さい。
さてインクというものは、単に色が異なるだけでなく性質も違います。
まず、紙に対して滲みの大小、裏抜けの大小、乾きの速度、耐水性、耐候性、インクフローの大小、など様々な個性があります。
更に万年筆との相性というものがあり万年筆との組み合わせによってインクフローや筆記感が変化するのが難しくも面白いところでしょう。
自分の万年筆に合ったインクを探し出すのも楽しみのうちかも知れません。
ではこのインクについて初歩的なことを解説をしましょう。
以下の説明は特別な例外を除いて一般的な事柄を説明します。
まずインクには水性と油性に分けられますが万年筆用インクは全て“水性インク”です。
なのでこれからは“万年筆用水性インク”について説明します。
万年筆用水性インクには“顔料インク”と“染料インク”とがあります。
これについて説明しましょう。
まず顔料インクについて。
顔料インクとは水に溶けない粒子(顔料)が主成分のものを指し、製図用インクなどがこのタイプです。
「水に溶けない粒子」がなんで“水性インク”やねん?
という疑問が出るでしょう。
簡単に言うと、顔料が水に“溶けている”のではなく、水に“混ざっている”状態です。
この顔料の粒子が紙に乗っかって乾燥することで線になりますので、まあ、ペンキと同じ原理ですね。
この水に溶けない粒子は一旦乾燥すると再度水には“混ざらなく”なるので乾燥後は耐水性があり、水で流れたり消えたりすることがありません。
しかも、顔料という粒子で構成されているので、比較的色が濃くはっきりしており紙に対しても滲みや裏抜けが非常に少なくシャープな描線となります。
長期間の保存で色が褪せることもなく保存用としては理想的なインクです。
あと、比較的粘度が高いので筆記感が滑らかになるということにもなります。
難点は色の種類がとても限られることでしょうか。
現在プラチナ社のカーボン・ブラックとセーラー社の極黒(きわくろ)の2種類しかありません。
つまり黒だけです。
透明感が無いのでベタッと濃い色になり、インクの濃淡が出にくいのを嫌う人も居ます。
もう一つの難点は前述したように耐水性があるが故に万年筆の中で乾燥させてしまうと固着したインクを水洗することが出来なくなり再起不能となってしまいます。
なので絶対に乾燥させないよう注意が必要です。
長期間使用しない場合には乾燥する前に完全に万年筆を洗浄します。
いいですか? 内部に僅かでも残るとだめなのでしつこく“完全に”洗うんですよ。
これが結構難しいのですが。
もしも、やらかしてしまった場合は、ロットリング・クリーナーのような洗浄液と超音波洗浄機のお世話になるハメになります。
次に染料インクについてですが、
染料インクには通常タイプに加えて、ちょっと特殊なタイプがあります。
特殊なタイプとは、いわゆる“古典インク”(或いは“化学インク”)と呼ばれるやつです。
古典インクについては後で説明するとして、通常の染料インクについて説明しましょう。
市販されている万年筆用インクの大半がこれで、紙に染み込んで繊維を染めることにより線を描きます。
非常に豊富な種類の様々な色が各社から販売されており、たとえば同じ“青”でも各社微妙に異なる“青”が販売され、どれを使おうか迷うほどです。
色もさることながらインクフローや耐水、耐候性も多種多様で選択に苦労します。
たっぷり流れの良いインクでヌルッと書くもよし、薄めの透明感のあるインクで色彩の濃淡を楽しむもよし。
「これだ!」というインクを探し出す楽しみも万年筆ならではなのかもしれません。
難点は、まず決定的に耐水性が劣ります(例外もありますが)。
そして耐候性が良くないこと、つまり長年の保存で色褪せてくることです。
特に直射日光にさらすと退色が酷くなります。
まあ、完全に消えて判読不能になるところまでいかないとは思いますが、気分のいいことではないですね。
「いいや、水には濡らさないし、日光にも当てない。」って人は気にすることはありませんが。
最近は耐水性や耐候性に優れたインクもあるようですので保存性を重視するならばそのような製品を選択してください。
更に前述の通り、染料インクは紙に染み込んで描くため多かれ少なかれ滲みや裏抜けが発生しますので紙の質にあわせたインクを選択する場合もあります。
先の染料インクの弱点である耐水性、耐候性の向上を目的としたのがこれから説明する“古典インク”で、俗に古典BBと呼ばれるインクです。
BBというのはブルー・ブラックの略で、ブリジッド・バルドーではありません。 ふっるー!
因みにCCとはクラウディア・カルディナーレ、MMはマリリン・モンロー、しかしながら至高はやはり、イングリッド・バーグマンでしょう。
グレース・ケリーも素晴らしいのですが、私としては・・・・・・
インクの話に戻ります。
古典BBは鉄イオンが含まれており筆記後の酸化作用で沈殿し定着させるというものです。
一部のメーカーのブルー・ブラックがこれにあたり、筆記後、時間が経過するにしたがって徐々に酸化して変色(水に溶けない性質へ変質)していきます。
これにより水に濡れても消えることなく良好な保存性を確保できるのです。
徐々に変質するので時間が経過するにつれて色が変わっていくのも特徴です。
欠点は色がブルー・ブラックしかないことと、通常の染料インクに比べて若干インクフローが劣ることです。
更に“水に強い”=“水洗できない”というわけで万年筆の中で乾燥させてしまうと鉄イオンが酸化して固着し水洗いで回復できなくなります。
又、鉄を溶かして製造されているせいか酸性の性質を持ちますので保管状態が悪いと万年筆の金属部分を腐食させる恐れがあります。
まあ、乾燥させない、使用せずに長期間放置しない、という万年筆の基本を守ればどうってことないのですが。
ここで注意しなくてはいけないのは全てのメーカーのブルー・ブラックが古典インクとは限らないということです。
代表的なメーカーの古典インクは、モンブラン、ラミー、ペリカン、プラチナですが、メーカーによってはボトルは古典インクでもカートリッジは違うってのもありますので、ちょっとややこしいですね。
おさらいすると。
黒しかないが、水に強く保存性が欲しいのであれば顔料インク。
水には濡らさない。万年筆に優しくて豊富な色を使いたい人は通常の染料インク。
黒は嫌だけど耐水性は欲しいという人は古典インク。
水に強いインクほど、もしペン内部で乾燥させるとやっかいであり、水に弱いのであれば万年筆に優しいインクということになります。
粘性の低いインクはインクの出が良い反面、紙に滲んだり抜けたりし易くなるが、粘性の高いインクはその逆、といったところですね。
このあたりのバランスが難しい。
さて、大体わかってもらえましたか?
以上が各インクの種類とその特徴です。
最後に使用上の注意として、重要なことを説明します。
インクは化学製品です。従って種類の違うインクを混ぜ合わせると化学変化によって性質が変化しますので絶対にやってはなりません。
但し、混合を保障しているメーカーもあります。
セーラー社のジェントルインクとプライベート・リザーブ社のインクです。
これは調合して自由な色を作成できることを保障している数少ないメーカーです。
安心感のあるメーカーですね。
これ以外のインクを混合するとどのような結果になるかは予想できませんので、やるのは勝手ですが後は知りませんよ。
さて、「混ぜてはいけない」理由は理解して頂けたでしょう。
これがなぜ重要なのかというとですね、もしも、あるインクを使っていたが気に入らなくなって、他のインクに変更する場合です。
当然、万年筆は奇麗に水洗いして古いインクを洗い流します。が、どうしても僅かではありますがペン内部に古いインクが残る可能性があります。
完全分解でもしなければ内部を完全に洗浄することが困難なのです。
何が言いたいかわかりますね?
そう、内部に僅かに残った古いインクと新しく入れたインクが混ざった結果、化学反応による様々な問題が出る可能性があります。
怖いですね。
だから完全に洗う自信がなければ、「一度入れたインクは永久に変更してはいけません。」
というのがメーカーや販売店の決まり文句です。
と、まあ、書いてはみましたが、大抵の人達は普通に洗ってインクの入れ替えなんか当たり前にやってますがそれでトラブった、てのは聞いたことがありません。
ですから皆さん、自己責任で思いっきり楽しみましょう。
2009年5月11日
(終わり)
|