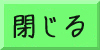万年筆についての基礎知識
万年筆というのは近年に於いて筆記具の中で主役とはいえません。
一般にボールペンやシャープペンシルに比べて桁外れに高価であり、しかもデリケートで手入れも必要、良質の紙でないと滲むわ裏抜けするわ、
筆記後もインクが乾くまで待たないといけない。
更に書いた後も水に弱い。
ペン先は僅かの衝撃で調子が悪くなり、更には気圧や温度の変化でインク漏れを起こす。
何でこんなモノ使うんでしょうね?
長所といえば、筆記に力が要らないので楽であること、インクのランニングコストが安いこと、の2点くらいでしょうか?
しかしこれは膨大な筆記量の職業人達ならばいざ知らず、一般の人達がそれほど大量にモノ書きするとは思えません。
しかしながら万年筆ほどマニアの心を掴んで止まない筆記具は無いのです。
それはなぜか? 実はよくわかりません(キッパリ!)。
多分、私の場合は機械式腕時計を好むかの如くノスタルジーを感じるのかも。
そして万年筆は大切に使えば非常に長寿命で、長く使う道具には愛着が出るのです。
そもそも私が万年筆を使い始めたのはですね・・・・・(略)・・・・・好きなんですよ。
万年筆の人気の理由を考えてみましょうか。
万年筆はライバルであるボールペンと比較して次の違いがあります。
1.描線に個性が出る。 つまり線に強弱が表れるので字が上手に見えますよ。(汗)
2.浅い角度で筆記できる。ボールペンは寝かしすぎると書けませんね。
3.軽い筆圧で筆記できる。これは大量筆記する人には決定的なアドバンテージです。
4.インク色が豊富である。だから楽しい♪
5.書き味(筆記感)が良い。
上記の項目の何れかが気になれば万年筆を使い始めることになるのですが、この第5項にある“書き味”という、なんとも魅力的であり悩ましい言葉。
これに琴線が触れると、“ただ万年筆を使う人”から“万年筆オタク”へと豹変します。
なぜならば・・・・(略)・・・・体験すれば分かります。
これこそ多くの万年筆オタクが最も重要視するファクターなのですから。
スルスル、サラサラ、ヌルヌル、ヌラヌラなどと表現されるこの“書き味”という魔物。
これらを求めて万年筆オタク達は日夜ネットショップを徘徊してポチり、ペンクリへ通う。
気が付けば多数のペンを手にしてニヤニヤしている。
とまあ、理由(経過)としてはこんなところでしょうか。どうですか?これを読んでいるアナタ。
ではこれから初心者のために万年筆の基本を少し説明しましょう。
万年筆というものにはインクが入っています。このインクで線を書きます。
インクを紙にくっ付けていく役目をするのがペン先です。これをニブと呼びます。
このニブというのが万年筆にとって大変重要で非常にデリケート且つ高価な部分です。
ニブはインクによって腐食しないよう金の合金が使われています。(安価なペンは違いますが)
18金や14金という表記は金の含有量を表し、18金ならば金の含有率が約75% 14金ならば約58%です。
当然18金の方が高価ですが、ペン自体の性能や書き味には何も関係ありません。
14金よりも18金の方が柔らかいなどというのは都市伝説(シッタカのデマ)であり迷信です。
ペン先の硬い柔らかいはその厚み、大きさ、形状で決まります。
超人的な感覚の持ち主でもない限り金の含有率によって体感できるような差はありません。
単に付加価値だと思ってください。
一方、安価な万年筆のペン先には金ではなく鉄の合金が使われており、腐食に強いステンレスが一般的です。(メーカーは“特殊合金”などとかっこよく書いている場合もあります)
鉄系合金は金と比べると硬く靭性が強いのですが、近年では金ペンと遜色のない筆記感を実現しています。
ここで言う筆記感とはあくまで“弾力”のことであり、“滑り”ではありませんよ。
んで、ニブの先端にはニブポイントと呼ばれる小さな球が溶接されており、一般にこの球はイリジウムという硬質金属の合金です。
筆記時に紙に接するのはこのニブポイントです。
なので紙に対する滑りはこのニブポイント(の形状や性質等)で決まります。
更にニブポイントの大きさと形で線の太さも決まります。
EF=極細 F=細字 MF=中細 M=中字 B=太字 BB=極太 ってやつですね。
下の写真がニブ(ペン先)です。先端部分の大きさ(幅)に注目。

このニブポイントは紙に接する部分であるが故に僅かな形状の差で書き味が大きく変わります。
ニブポイントの状態が筆記時の“滑り”つまり滑らかさを決定するのですが、現在の製造技術ではどうしてもこの球にごく僅かなばらつきが生じるので
同じペン先のつもりで製造しても太さや書き味が違ってしまうのです。
万年筆購入時に試し書きして選ぶのはそのためで、自分の書き方に合うペン先を見つけましょう。
いやー、微妙ですねー。こういう微妙さが他の筆記具にない個性と言えるでしょう。
決して「な〜んや、均一に作る技術が無いだけやがな。」というツッコミをしてはいけません。
“個性”なのです。
そしてそして、長年に渡って使われてきた万年筆はその使用者の筆記角度や筆圧などの条件でニブポイントが磨り減ってきます。
つまり、使用者の書き癖に合わせてニブポイントが磨耗してどんどん滑りが良くなってくるのです。
使えば使うほど万年筆の書き味が良くなってくるんですよー。まさに“育てる”という表現ぴったり。
こういうところも万年筆を手放せなくなる理由の一つなんですね。ロマンですね。
次に万年筆にインクを入れる方式について説明しましょう。
万年筆は内部にインクが必要です。しかし書いているうちにやがてインクは無くなります。当たり前。
しかしインクが無くなっても新しい万年筆に買い直す必要はありません。
インクを補充できるのです。 エライ! エライぞ万年筆!
んで、インクを補充する方式が万年筆によって異なります。
まず、吸入式と呼ばれるタイプですが、これは海外の高級モデル等に多く採用されている方式で、万年筆内部にポンプ機構が備わっています。
この機構もいくつかの方式がありますが、一般的なのはピストンで吸い込むタイプです。
大抵はお尻部分を回転させると内部のピストンが上下し、あたかも注射器か水鉄砲のようにインクを吸い込むことが出来ます。
一旦ピストンを押し下げ、万年筆のペン先をどっぷりとインク瓶に浸けてからこのピストンを元の位置に引き上げることによって瓶からインクを吸い込みます。
面倒(この作業が好きな人も居る)ですが、インクを瓶から直接補充することができるので瓶入りインクであればどのメーカーの製品でも使えるメリットがあります。
欠点としては、
・面倒
・瓶を倒す可能性がある
・手を汚す可能性がある
・吸入の度にペンの首軸が汚れる
・ペンの首軸より液面が下がると吸引できなくなる(例外も有りますが)
・何度も繰り返すとペン先に付着した埃や繊維クズが瓶に溜まる
・吸入機構のメンテナンスが必要
とまあ、メリットは無さそうですが、吸入の作業が楽しいと感じる人も居ます。
海外の高級品に多く採用されているせいか、特に初心者は憧れるようです。

次にカートリッジと呼ばれるインクのタンクを交換する方式です。
インクが無くなれば、空になったカートリッジを抜き、新しいカートリッジと交換するだけ。
瓶インクよりも少し割高ではありますが、簡単、楽チンですね。
現行の多くの万年筆がこの方式です。(因みに、我らがセーラー万年筆の特許ですよ)
欠点としては、
・吸入式に比べ、インク量が少ない
くらいですか。
インク量が少ないとは言っても大量筆記しない人には問題は無いでしょう。
筆記量の少ない人ならインク量が多いと使い切るのに時間がかってしまいインクが煮詰まってしまうので容量が多すぎるのも考えものです。
又、吸入機構という可動部が無いのでメンテナンスが不要で故障の心配が無いのも有利。
ところが喜んでばかりはいられません。カートリッジ方式には弱点があります。
それはメーカーによってカートリッジが異なるために他メーカーのカートリッジが使えないのです。
A社の万年筆を使っていればA社のカートリッジしか使えないということ。
互換性のある共通規格のカートリッジを採用しているメーカーもありますが、それでも全てのメーカーのカートリッジを使うことはできません。
悲しい現実ですね。なんで全メーカー共通にしないのか・・・・・・
と、ここで文句を言っても仕方ないのでやめましょう。

もし他のメーカーにすんごい奇麗な色のインクがあっても目に涙を溜めて諦めるしかないのでしょうか?
いいえ、神は我々を見放しません、このような悲しい現実を打破する方法があります。
それはコンバータという部品で、これはまさにカートリッジとほぼ同じ形をした吸入機構です。
コンバータには吸入式万年筆と同様にピストンの機構があり、こいつをカートリッジの代わりに装着すれば擬似吸入式として動作するスグレモノ。
インク補充のやり方は前述の吸入式と全く同じ。
万年筆のペン先をどっぷりとインク瓶に浸けてコンバータのツマミをクリクリ回すのです。
ちょっと姑息な気もしますが、まぁいいでしょう。
カートリッジの互換性という呪縛から開放されるのです。
当然のことながらこのコンバータもカートリッジ同様、各社専用のものが必要ではありますが、一度購入すれば何度でも使えますので便利ですよ。
ピストン機構の分、カートリッジに比べ若干インク容量は少なめですが、瓶インクであればどこのメーカーのインクでも使えるようになります。
お店へ行って「ボトル・インクください!」と大声で言えるようになります。
さあ、偉そうに吸入しましょう。よかったですね。
但し、吸入式の欠点とカートリッジ式の欠点を全て踏襲することになりますが。

参考として各社のカートリッジの互換性をざっと教えます。
(注)もし合わなくても私に文句を言わないように。
原則として自社のカートリッジとコンバーターしか使えないメーカー。
セーラー、プラチナ、パイロット、パーカー、シェーファー、クロス、ラミー。
ようするに国産3大メーカーとアメリカ3大メーカー、それにラミーです。
(注1)プラチナ製品には一部欧州規格のカートリッジ仕様のもの有り。
(注2)プラチナ製品には専用アダプターを取り付けて欧州規格のカートリッジが使える場合有り。


一応、欧州規格のカートリッジが使えるメーカー。
一部の例外を除き、前述のメーカー以外は欧州規格のカートリッジ、コンバーターを使用します。
具体例だと、モンブラン、ペリカン、ウォーターマン、アウロラ、デルタ、ロットリング、レシーフ、etc....
但し、ロングタイプとショートタイプがあるので若干の注意は必要です。
そして第3の方法
これは私が最も多用している方法なのですが、単純に瓶のインクをシリンジ等を使って空のカートリッジに充填するやり方。
これだと瓶に埃やゴミ等は溜まることは無く、瓶のインクを最後まで使い切ることができます。
瓶をひっくり返してしまうリスクも下がるでしょう。
皆さん、使い終わったカートリッジは捨てずに、綺麗に洗い、よく乾燥させて有効活用しましょう。
万年筆のお手入れ
万年筆は毛細管現象を利用してインクを供給します。
内部は非常に細かな構造をしており、もしも内部でインクが乾燥、或いは固まると万年筆は致命的なダメージを受けます。
ですから万年筆は絶対にインクを乾燥させてはいけません。
常に使用して絶えずインクを供給させて乾燥させないようにする。
これが最も基本的な万年筆のメンテナンスと言えるでしょう。
もういちど言います、常に使用していること。です。
できれば毎日、少しづつでも何か書くようにしましょうね。
そして、長期間使わないようであれば内部のインクを完全に洗い流してから保管しましょう。
これは、インクを変更する場合にも同じことが言えます。
古いインクは完全に洗浄してから新たなインクを入れます。
決して異なるインク同士が混ざることのないようしてください。
吸入式であれば、何度も吸排水を繰り返して徹底的に内部を洗浄します。
しつこいくらいやります。
カートリッジ式の場合はコンバータを装着して同じく何度も吸排水を繰り返します。
流水でひたすら洗い流したつもりでも内部にインクが残ります、必ず強制的に吸排水しましょう。
「流水で洗って、よく乾燥させる・・・」などと言う人もいるようですが、流水で洗うだけでは不充分な場合が多く、
しかも内部まで完全に洗えない限り乾燥などさせてはいけません。
保管時には水を入れておくほうが安全でしょう。
私は下の写真のように空きカートリッジにゴムのスポイトを取り付けたものを自作して使っています。
これに水を吸わせて万年筆にセットし、ジュボーっとペン内部のインクを押し出します。

どうです? 少しは役に立ったでしょうか?
大切な万年筆です、ちゃんとして使ってあげれば一生涯使えます。
使えば使うほど貴方の書き癖に合わせてくれる。
良い相棒になりますよ。
2009年5月11日
(終わり)
|